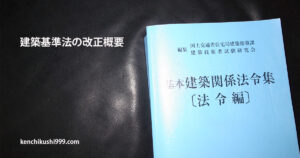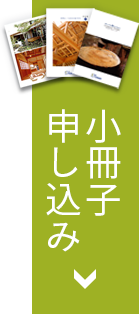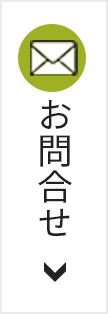建築基準法改定の影響
高気密・高断熱・高耐震の省エネ住宅に特化した「世界に1つだけの家づくり」株式会社六花舎設計、広報部です。
4月から、建築基準法が大きく変わりました。
建築基準法の改正の多くは、大規模な自然災害による被害が発生するたびに行われてきました。大地震や大型台風、火山の噴火といった自然災害のほかに、ビル火災などの事故や事件が起きたあとにも改正されています。また東京五輪や大阪万国博覧会の開催など、社会のニーズに合わせて改正されたこともありました。1950年に制定された建築基準法は、より安全で安心できる建物にするために時代の変化や建物技術の進化などに合わせて改正が行われているのです。
今年の建築基準法改正の目的は、 建物の省エネ性能を高めること です。 2030年の温室効果ガス46削減、2050年のカーボンニュートラル達成には、建物の省エネ化が不可欠です。 建物を建築する際には多くの重機を利用し、温室効果ガスを発生させ、建築材料を作るにあたって環境を破壊します。 建築時の温室効果ガス発生を抑制するのは難しいため、生活で発生する量を抑えるのが目的です。
メリットは、①行政が構造をチェックするため欠陥住宅が減る ②断熱性能の高い家になる ③耐震性の高さが一定以上になる。
デメリットは、①建築費用が増加する ②建築に必要な工期が長くなる ③デザイン性の高い家がたてにくくなる
どんなものにも、すべてメリット、デメリットがありますね。
具体的な改正ポイントですが、
1.省エネ基準の義務化 これまでは延べ床面積300㎡以上の建物だけが対象だった省エネ基準への 適合が、住宅すべての新築建築物に義務化になりました。そのため、省エネ性能を満たす設計や建材が必須となり、断熱や設備の基準が厳しくなりました。
2. 4号特例の縮小 今までは2階建て以下または500㎡以下の木造住宅は、建築確認申請で構造計算が免除される4号特例がありましたが、この特例の対象が大幅に縮小され、大半の住宅、リフォームで構造計算や確認申請が必要になり、耐震性や安全性のチェックが厳しくなり、手続きは必要書類が増えました。
3.木材利用の促進と構造規制の合理化 中規模以上の木造建築物で、構造計算が見直され簡易な計算で建てられる範囲が拡大し、大規模木造建築物の防火規定が一部緩和され、木造を使った建物が立てやすくなりました。
弊社では、建築基準法に関する最新情報に基づき、お客様の状況に応じたアドバイス・サポートを行っております。
お困りのことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。